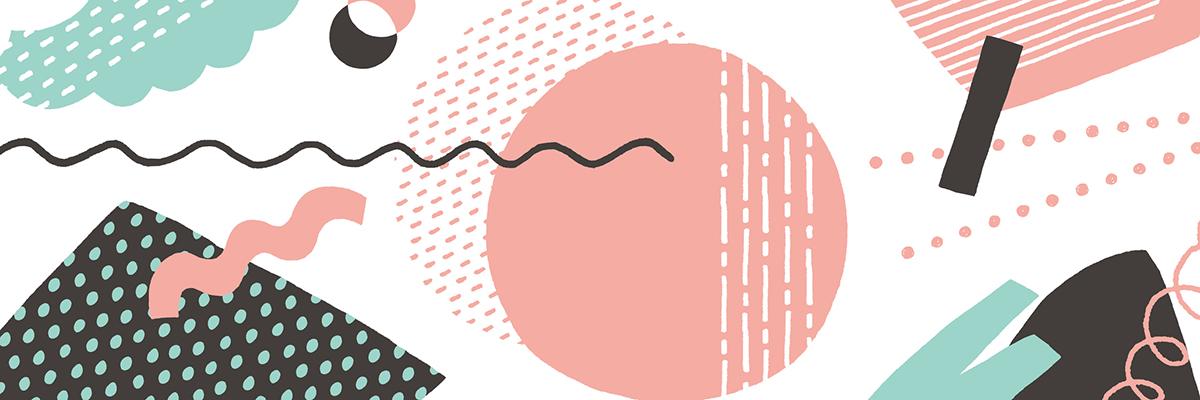たとえば家族や親しい友人が、がんで余命宣告を受けたとする。あなたはなんと声をかけるだろうか。「がんばって」? 「何でもしたいことを言って」? それともただ黙って寄り添う? 人生には解決できない苦しみがある。そのときに私たちはどう向きあえばいいのか。
千田恵子さんは、ホスピス医の小澤竹俊さんとともに「エンドオブライフ・ケア協会」を創設。生きていくなかで多くの人が遭遇する「自分が誰からも必要とされていない」という苦しみを抱えた人が「自分はここにいてよい、生きていてよかった」と思える社会に向けて、その関わりができる人材の育成や学校教育などの活動をしている。
父の難病が自分の使命を考えるきっかけに

千田さんが今の活動を始めたきっかけは、2011年に父がALSと診断されたことだった。ALSとは、次第に体の機能が失われていく難病だ。千田さんの父は、診断から1年ほどかけて、だんだんとできたことができなくなり、「寝たきり」の状態となった。
「母1人に介護を任せきりにするわけにもいかず、きれいごとではない家族介護の緩衝材としてせめて笑いを提供できないか」と思って、自分の役割を探すように帰省するようになった。介護の資格を取り、ほそぼそと手伝いながら、次第に実家中心の生活となっていった。これからどうなってしまうのかという得体のしれない不安感はあった。しかし、職場がITベンチャーで、海外と深夜までやりとりする勤務形態だったことから、社長が理解を示してくれて在宅で勤務するように。
父は2014年10月に亡くなったが、そのころ、千田さんは退職する決意を固めていた。「自分は会社に必要とされていない、と思ってしまったんです」
職場事情は恵まれていた。みんなが千田さんの状況を理解してカバーしてくれた。「だから仕事は私がいなくても回りました、でも逆に自分の存在意義が感じられなくて……」
もう一つ、母に言われた言葉もひっかかっていた。
「『あんたにはわかんないよ』と言われたんです。母を一生懸命励まそうとしたら、『そんなこと言わないでよ』と……。無力感に襲われて」
しかもその母も、父の死の3か月後に突然死してしまう。千田さんは仕事をする意味、生きる意味について思い悩んだ。漠然と「いのち」にまつわる仕事をしたいと思っていたが、資格もなく、何ができるかもわからなかった。
そんな時に、ホスピス医の小澤竹俊さんと出会う。小澤さんはホスピスで勤務医として働いたあと、在宅のホスピス医としてクリニックを立ち上げていた。小澤さんと話すうちに、「これは自分がやることだ」と直感を得て、次第に千田さんは自分の「やるべきこと」がはっきりしていった。
15年4月、「エンドオブライフ・ケア協会」を創設し、今は小澤さんが代表理事、千田さんが業務執行理事となっている。もともと小澤さんが千田さんの会社の社長の間接的な知り合いだったこともあり、会社は辞めずに籍を置いたまま、社団法人の活動をしている。
人材育成やセミナー、授業を通していのちと向き合う
活動の柱は3つ。1つは、人生の最終段階を迎える人が、地域で最期まで自分らしく暮らせるようにするための人材育成だ。看護師や介護関係者、医師などに研修を行う。言ってみれば、「みとりのケア」だ。ホスピスという解決困難な苦しみをかかえた人と関わる現場で学んできたことを体系化したプログラムを、すでに7400人以上が受講をした。
また、働く世代、特に企業向けにセミナーを行っている。高齢者の子ども世代にあたる40代50代は、多くの場合、企業にとって貴重な戦力だ。一方、家族の介護、子育てなど、プライベートのさまざまな困難と仕事を両立させていく悩みを抱えている。ここでも、ホスピスのマインドがヒントとなる。
それから、「折れない心を育てる いのちの授業」が3本目の柱だ。単に命が大事、ということではない。「自分も他者も、かけがえのない存在であるということに気づくための教育です」と千田さん。といっても、生きるということはつらさや苦しみも多い。何よりも、死は誰にも訪れるものではあるが、時に理不尽だ。自分も、周囲の人々も、どう向き合っていけばいいのか。
問題解決がゴールではない。相手の気持ちを受け止める

対象は小学生から大人まで。学校の授業として行われることもあれば、地域の公民館が会場のこともある。「授業」は、こんなふうに進んでいく。
たとえば、スポーツの試合。自分のミスで負けてしまった子がいる。「自分のせいで負けたんだ」と落ち込む子に何と声をかけるべきなのだろう。「多くの場合、わかるよと共感を示したり、大丈夫だよ、がんばったじゃない、と励ましたり慰めたりするのですが、他人である私が相手の苦しみを本当にわかることはできるでしょうか? 私は、できないと思うんです」と千田さんは言う。
「相手との関係性にもよりますが、落ち込んで苦しんでいる人の気持ちを本当に理解することは本当に難しい。そこをわかった気になって声をかけると、かえって『僕(私)のことなんて何もわかっていないくせに』と反発を招いてしまうこともある」
思いあたる人も多いのではないだろうか。安易に共感しようとしてこじらせてしまったり、優しく声をかけてくれた相手に腹をたててしまったり。ではどうすれば?
「目の前で苦しんでいる人のことを理解したいと思う気持ちはすべての始まりです。でも、どんなに理解したいと思っても、私にはあなたの気持ちを理解することはできない、という前提に立つと、話の聴き方が変わります。自分が知りたいことを質問し、わかった気になるのではなく、相手から出てくるマイナスの言葉も否定せずにそのまま返す。あなたはそう思うんだね、と相手が言いたいことを認める。これを反復と言います。そして、次の言葉が出てくるまで待ちます。
私が何かいいことを言うのではなく、相手の問題を解決しようとするのではなく、相手の言葉を受け止めること。このやりとりを通して、相手が、この人は自分の苦しみをわかってくれた、と思えることがゴールです。つまり、主語が違うんです」
そして、相手からさらに自分にも向き合っていく。
たとえば、バスケ部に2人の子がいる。1人はけがをして試合に出られなかった。もう1人は大活躍をした。けがをした子が自分は役に立たない存在だ、自分なんていなくてもいい存在だ、と思ってしまう。これもまた誰にでもある経験だろう。
「その時、試合に出た子が、けがをした子の話に耳を傾ける。否定せず、言葉を遮らずに、相手の言葉を反復し、次の言葉を待つ。すると、誰にもわかってもらえないと思っていた、自分の苦しい気持ちを、この人はわかってくれた、認めてくれたと思える。このやりとりを通して、うまくいかない自分であっても、存在を丸ごと認めてくれる友達がいるんだと思えたときに、自分はこれでいいと思える可能性がひらけます。
それは、人とは限らないし、目で見えるものとも限りません。私の場合であれば、亡くなった父母が、いつも見守ってくれています。うまくいかないとき、とても自分自身はよくできました(Very Good)と思えなかったとしても、父母なら私に今何と声をかけるだろうかと思い浮かべることで、自分のことを『これでよい』(Good enough)と思うことができます」
そして授業は、「自分が苦しいときには、勇気を出して声を上げてほしいし、もし、誰かが苦しんでいるときには、あなたが、たった1人の『わかってくれる人』になれるといいですね」と結ばれていく。
小さな輪の連鎖で、互いに気にかけあう社会を

授業終了後には、こんな感想が寄せられる。小学生が書いたものだ。心の中から言葉があふれ出すような長い文章を寄せてくれる人が少なくないのだという。
「これからは、解決できる苦しみは、自分で解決し、解決できない苦しみは家族や先生に相談することがこのじゅぎょうで分かりました。私も、早くこの世からいなくなりたいと思っていたけど、このじゅぎょうを受けて、もう少し生きようと思いました。様々なことを教えてもらったので、苦しいことがあればこのことをおもいだす。と思いました」
「この2時間のじゅ業を通して分かった事や心にひびいた事は、みんなにささえられて生きてるんだということです。ぼくはみんなの役にたてずきずつけてばっかりでした。今日のじゅ業であらためて思いました。なので、次からみんなの支えになっていけるような人間になっていきたいです」
「1人の支えがあるだけでも、うれしい人はたくさんいるんだったら、100人1000人10000人の人たちが支えてくれたらもっともっとうれしいんだとよく分かりました。だれかに支えられたら、次はその子を支えたり、いろんな子を支えればいいんだと思いました」
※ 表現は原文ママ
どうだろう。子どもたちのやわらかな心が多くを吸収した様子が目に見えるようだ。
千田さんも、多くの授業に立って子どもたちの変化の様子を目にしてきた。
「半径5mのなかで、お互い気にかけあう社会を作りたい。自分が誰からも必要とされていない、居場所や役割が感じられない、と悩み苦しむことが、人生のなかで、自分や身近な人に何度も形を変えて繰り返し訪れる。そのときに、誰もが、誰にでも、本人にとっての『わかってくれる人』『支え』になれる。
このホスピスのマインドは、一部の専門家が一部の人にしかできないことではなく、ユニバーサルなものだと思うのです。そして、この小さなコミュニティの輪が、そこかしこで連なっていく。それが、良い最期を迎えられることにつながるのだと思うんです」
今、千田さんは、「やりたいこと」を見つけ、その目は明確な未来に向けられている。